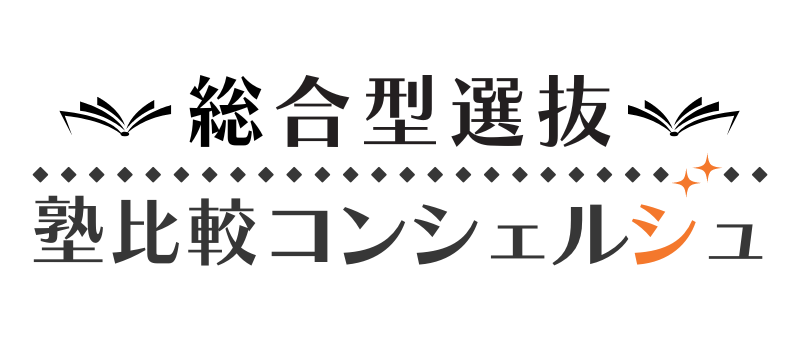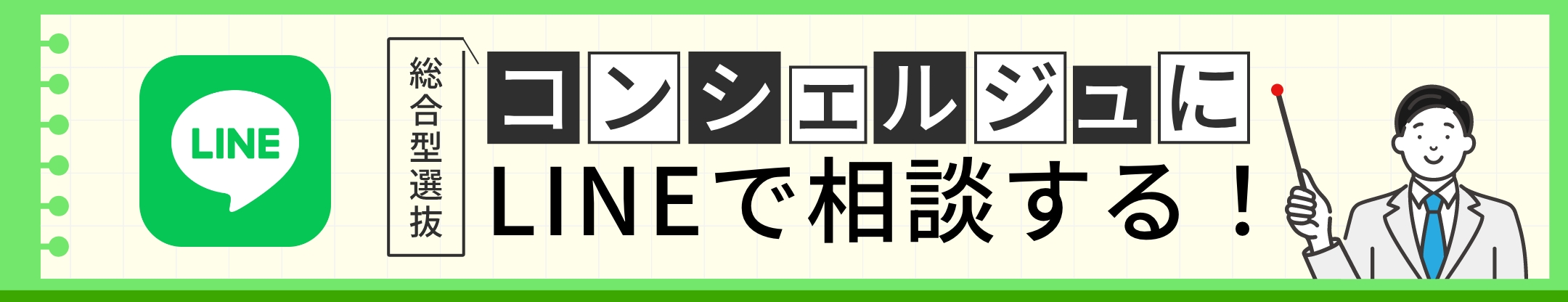総合型選抜の面接の注意点
2025/01/11
総合型選抜入試は多面的な人物評価をおこなうため、面接試験を課す大学学部が多いです。
一次試験として書類や小論文を課し、その合格者に二次試験として面接を実施する大学などもあります。
この記事では、総合型選抜の面接試験で気をつけたいことを確認します。
➀面接の目的
大学側は様々な書類を提出させたうえで、なぜさらに面接を実施するのでしょうか。
一言で言うとすれば「受験生の思考の深さ、中身の真価を見ている」と考えておくとよいと思います。
乱暴に言えば、書類は誰か大人に代筆させることができます。実際、学校の先生や塾で添削指導を受けたり、家族からアドバイスをもらうことは往々にしてある、というかそっちのほうが恐らく普通です。
ということは、大学が受け取る出願書類には、受験生の本来の実力以上のものが出ていたり、文面としては立派なことが書かれているけれども、実際本当のところはどうなのか疑わしかったりという状態が発生しているわけです。
そこで面接をして対話をすることにより、その受験生の「実態」を測っているわけです。
大学にとって、面接を実施することはかなり負荷の大きいことです。教授たちを面接官として配置し、何人もの受験生と面談させることには相当なコストがかかります。
しかし受験生の実態を見極めて、本当に入学にふさわしい人を選抜するために、大学側は面接試験を実施しているのです。
②面接の評価
面接試験対策の方法を紹介する前に、面接で大学側がどのように受験生を評価しているのかを理解しておきましょう。
もちろん大学学部によって評価方法や評価基準は様々であり、その内容は非公開です。ですのであくまでも一般論になります。
評価は基本的には「ルーブリック」というものを使って行われます。
例えば
➀アドミッションポリシーに合致している 1 2 3 4 5
②学習計画が明確である 1 2 3 4 5
③主体的に探究できる力がある 1 2 3 4 5
④論理的に思考し、表現することができる 1 2 3 4 5
というように、大学側が必要だと思う素養を項目にし、それを5段階や7段階で評価しています。
残念ながらペーパーテストのような明確な正解があり、点数がはじき出されるものではありません。
上記のような評価方法である以上、その面接官個人の主観に基づく評価がベースになります。ここが総合型選抜入試の難しいところです。面接官との相性に左右される部分も少なからずあります。しかしそこはブラックボックスですので、仮に不合格だったとして、何が悪かったのか知る術はありません。
③面接で必ずされる質問とポイント
とはいえ、しっかりと対策をすれば面接試験で高評価を得ることは可能です。しかし簡単ではありません。
ⅰ)探究や活動実績に対する深堀り質問
まず最も重要な対策は「自身の探究を実体験に根差して深く理解していること」です。
前述の通り、志望理由書や自己PR書などの書類を通して、受験生が何を学びたいのか、どんな活動をしてきたのか面接官は既に知っています。そしてそれを本当に受験生が心からやりたいと思っているのか、精力的に活動してきたのかを探ろうとしてきます。
それを探るために、面接官は「掘り下げ質問」をしてきます。
「●●を探究していたんだね。そこで1番苦労したことはなに?」
「●●をやっていたんなら、きっと■■が難しかったと思うけど、それはどう乗り越えた?」
「●●の研究に関しては△△大学が有名だけど、なんでうちの大学なの?」
「●●って既に多くの人が研究しているけど、今からあなたがやる必要性はどこにある?」
下の2個はなかなか意地悪な質問ですが、SFCなどの難関大では当たり前に質問されます。
大学教授はその道のプロです。受験生の探求テーマの魅力も難点も大体経験してきて分かっています。ですから、受験生が本気で主体的に活動しているのかどうかは、上記のような質問に対する回答の中身の濃さを聞けばすぐに分かってしまいます。
よって「自身の探究を実体験に根差して深く理解していること」が最重要となるわけです。
ⅱ)志望理由に関する質問
志望理由書を提出する大学学部でも、面接で改めて志望理由を聞かれることは多くあります。志望理由において重要なことは「志望理由書の書き方」の記事を確認してみてください。
そのうえで、面接で志望理由を語るときに気をつけたいポイントは2点です。
・志望理由書に書ききれなかったソフトな情報を追加する
・身体全体で熱意を伝える
志望理由で絶対に欠かせない情報は「なぜその大学学部でなければいけないのか」でした。しかし書類には字数制限があるため、その重要ポイントを書いただけで字数いっぱいになってしまうこともあります。そこで面接では、追加情報を言葉で伝えましょう。
例えば、オープンキャンパスで感じたこと、教授や学生の言葉で感銘を受けたもの、自分がそのときどのような気持ちになったかなどは、なかなか細かく書類に書くことはできません。しかし言葉であれば臨場感を持って自分の想いを伝えることができます。
そして是非それを伝えるときには熱意を込めてください。面接官の目を見ること、大事な部分で語気を強めること、身振り手振りを加えることも効果的です。
対面の面接でしか伝えられない情報が必ず存在しますので、それを余すことなく表現しましょう。
④面接試験の対策方法
では具体的にどのような準備、練習をしておけばよいのでしょうか
ⅰ)王道の質問に対して回答を準備する
いわゆる鉄板質問というものがあります。
志望理由、自分の長所短所、高校時代1番頑張ったことなど、聞かれる可能性が高い質問については、1度文章に書き起こすなどして回答を作っておきましょう。
ⅱ)自分が受験する大学学部の面接試験情報を集める
上記に加え、自分が受験する大学学部の面接試験で過去にどのような質問がされたのか調査しましょう。
ネット検索、学校の先生にOBのアンケートを見せてもらう、塾でデータをもらう、先輩に聞くなど、ここは頑張って行動し、情報を集めましょう。
もちろん本来あるべき姿は、面接試験のその場で面接官から聞かれたことに対して、自分の想いや考えを自分の言葉で紡ぎ出して回答することです。
ただ、それが納得のいくレベルでできるためにも、事前準備は重要です。準備のために色々と考え、頭の中を整理し、言葉にする作業も、自分の探求を深める一助になります。
ⅲ)口に出して練習をする
回答の準備が頭の中や文章化することによって整ったら、必ず喋る練習をしてください。
頭の中にあるものを言語化することは、得意不得意の分かれるところです。せっかく良い考えがあっても、うまく言葉にできなければ相手には伝わりません。
想定される質問に対する回答は、何度も声に出して練習してください。そのうち勝手に言葉が出るぐらい、自信をもって話すことができるようになるはずです。
このときに大切なことは「誰かに見てもらう」ことや「スマホで録画する」ことです。
面接をうまくいかせるためには話の内容だけではなく、全体的な「印象」が重要になります。
例えば自信なさげに下向き加減で喋っている人は、例えその内容が素晴らしくても面接官を不安にさせてしまいます。
声の明るさ、大きさ、表情、目線、身振り手振りなどを必ずチェックしてください。
ⅳ)(できれば)専門家に模擬面接をしてもらう
最後に仕上げとして行いたいのが、本番を想定した模擬面接練習です。
面接試験はナマモノです。色々と回答を用意しても、全く想定していなかった質問をされることはもちろんあります。また面接はひとつのコミュニケーションですから、あなたの回答に対して、それに紐づく次の質問がなされ、深く深く話を掘り下げられることもあります。
そういったケースに臨機応変に対応するためのトレーニングもしておきたいところです。
学校の先生に頼んだり、専門塾で実施してもらうのが一般的ですが、できればここまで練習をしておきましょう。