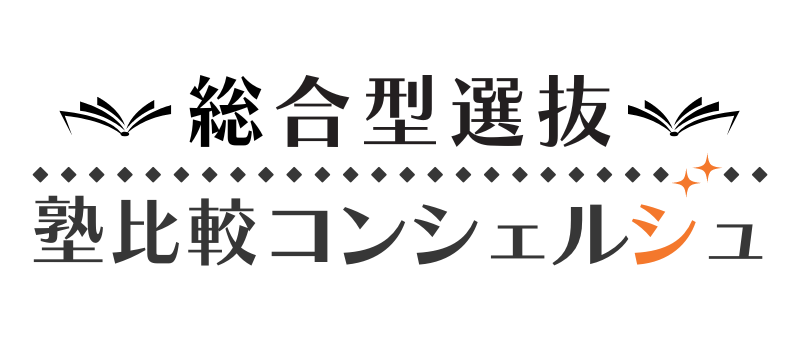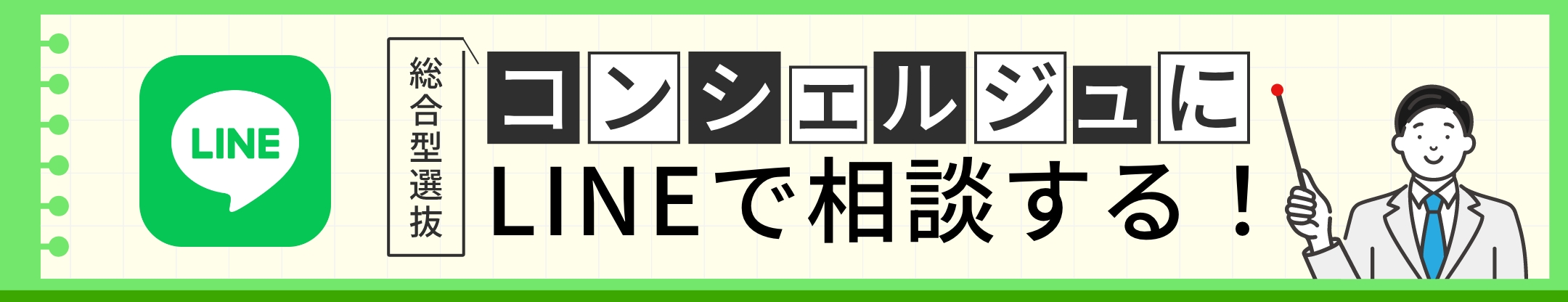志望理由書の書き方
2025/01/11
総合型選抜入試において、多くの大学で提出書類のひとつに志望理由書が求められています。
また、仮に志望理由書が不要だとしても、面接で結局志望理由を聞かれるなど、総合型選抜において志望理由は大変重要なピースです。
この記事ではそんな志望理由書の作成において大切なことを紹介したいと思います。
なぜ志望理由が求められるのか
総合型選抜入試は、受験生と大学の相性を測る試験です。
受験生が大学で学びたいと思っていることが、本当にその大学学部で実現できるのか。その大学学部で学ぶための素養を身につけているのか。書類や面接を通して、大学側は受験生をよく観察して合否の判断を下しています。
志望理由書は「なぜこの受験生はうちの大学で学びたいのか、学ぶ必要があるのか」を大学側が知るための書類です。
志望理由の中身が「べつにうちの大学じゃなくてもいいんじゃない?」「そんな中途半端な想いで入学しても、この子は大成しなさそうだな」と思われてしまうものであれば、合格をもらえることはないでしょう。
その点をよく理解したうえで、受験生は自分の想いを伝える必要があります。
志望理由書の中に絶対に書くべき内容
志望理由書が合否の判断においてどのような意味を持つのかを確認したところで、具体的に志望理由書の中で表現したい項目を挙げてみます。
・その大学学部でなければならない理由
・その大学で学びたい具体的な内容や研究計画
・大学で研究を深める前段階として今現在注力していること
・そのような研究をしたいと思うに至った理由やきっかけ
上記が志望理由書の中で必要となるピースです。
ただし大学によっては志望理由書以外に「学習計画書」などを提出させるところもあります。そのようなときは志望理由書には細かい研究計画は書かず、学習計画書に記載します。
指定された制限字数などによって入れ込める内容は増減しますが、上記4点を意識してください。
中でも一番大切なのが「その大学学部でなければならない理由」です。
志望理由書はよくラブレターに例えられます。ラブレターを好きな人に渡すとき「まあ他の人でもいいっちゃいいんだけど、でも結構好きなんで付き合ってください」と書く人はいないですよね。「絶対にあなたじゃなきゃダメなんです!大好きなんです!」という気持ちを表現すると思います。
志望理由書を受け取る大学側の気持ちを考えてみてください。大学のことをよく調べていない、具体的に大学で何を学びたいのかも伝わってこない・・・そんな志望理由書を出してくる受験生に合格を出そうとは思いません。
ただし「その大学学部でなければならない理由」をはき違えてはいけません。例えば「尊敬する先輩が通っているから」「家が近いから」「就職率がいいから」などは、受験生本位な理由であり、本質的なものではありません。大学からすれば「だから何?」というレベルの内容です。
大学は研究機関であり、大学生は学びたい、研究したいことがあるから大学に通います。それが本質です。その本質に則った志望理由を持っていなければなりません。
ということで「その大学学部でなければならない理由」をもう少し掘り下げてみると
・その大学にしかない特長(施設や授業コンテンツ)に魅力を感じている
・その大学学部にいる教授に魅力を感じている
すなわち「自分の学び、研究を実現できる環境がある」というのが理由のど真ん中に表現されるべきかと思います。
それがしっかりと表現できたうえで、さらにそれを補強して相手に納得感を与える工夫をします。
そこで有効なのが「大学で研究を深める前段階として今現在注力していること」や「そのような研究をしたいと思うに至った理由やきっかけ」になります。
大学側の気持ちをまた考えてみましょう。
「●●を学びたくて、それが実現できるのは貴学だけなんです!入学させてください!」というアピールと
「●●を学びたくて、それが実現できるのは貴学だけなんです!その学びの前段階として私は既に■■な活動を続けています。なぜなら幼少期に△△な体験をして、絶対に学びたいと思ったからなんです。入学させてください!」
というアピールでは、やはり後者のほうが説得力や執念を感じますよね。
制限字数にはよりますが、「その大学でなければならない理由」がきちんと書けたら、あとはそこに説得力を加えられるようなピースを追加していきましょう。
上記内容を網羅できれば、他の受験生と差がつく、大学教授に伝わる志望理由書ができあがるはずです。
ただお分かりの通り、それには受験生が大学についてよく調査、研究することが不可欠です。
その大学でなければならない理由は、その大学のことも、それ以外の大学のことも調べて、比較して、魅力を探しださなければなりません。
教授の具体的な研究テーマや、授業のシラバスなども目を通す必要があるかもしれません。
そこまでやって初めて、自分の本気度が伝わる志望理由書が完成するということを覚えておいてください。